【インタビュー】密なコミュニケーションで、視点の違いを埋める
目次
- 担当者
- 使いやすく改善しやすい、新たな行政機関の窓口を作る
- バックグラウンドが異なるメンバーのコミュニケーションをつなぐ
- 各府省庁との立場や視点の違いを理解し、ずれを調整することが大切
- 行政官の仕事こそ、利用者視点であることを再認識してほしい
- 関連ページ
担当者
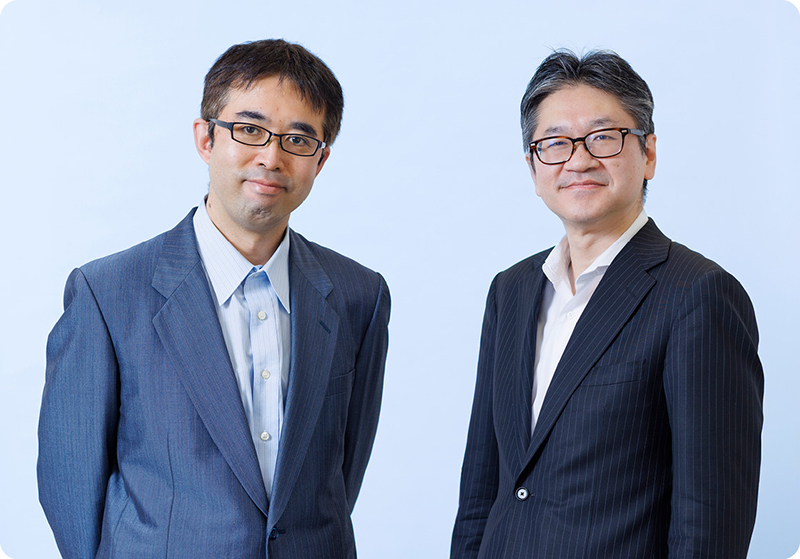
参事官 大塚 祥央 (写真左)
1998年警察庁に入庁。サイバーセキュリティ、情報管理、生活安全等の部署を経て、2024年3月から、現職(デジタル庁参事官)にて、マイナポータルや各種事業者関係システムを担当。
参事官 上田 尚弘 (写真右)
1999年厚生省に入省。介護、福祉、年金等の部署を経て、2022年6月から、現職(デジタル庁参事官)にて、医療DXやマイナポータルを担当。
※所属・職名などは2025年4月1日現在のものです。
使いやすく改善しやすい、新たな行政機関の窓口を作る
―この取組における、目的や課題を教えてください
大塚 マイナポータルは、国民にとって行政機関をより身近なものに変え、デジタル社会の基盤になる存在として、行政手続の効率化により、国民一人ひとりの人生に寄り添う新しい行政機関の窓口になることを目指しています。
上田 リニューアル前は機能自体が少なく、当初は、使える機能を個別で増やすことに注力していました。そのため、全体で見たときの動線が分かりにくく、改修も難しい仕様になっていました。そこで、フロントエンドとバックエンドを分離して、それぞれに強みのある事業者に委託し、利用者の声に応じて随時改善ができる開発体制を築いていきました。この取組は、デジタル庁のみならず、府省庁を越えて、「国民に分かりやすいサービスを提供していこう」という変革のきっかけになったプロジェクトだと捉えています。
バックグラウンドが異なるメンバーのコミュニケーションをつなぐ
―行政官としてどのような役割を担っていたのでしょうか
大塚 私が担っているのは、一つひとつの機能をリリースしていくに当たって、様々な角度から検証しながら、チームのコミュニケーションをつないでいくことです。マイナポータルのチームは大規模な組織です。中央省庁で働く国家公務員から、国民に近い視点で行政サービスに関わってきた自治体職員、民間企業から入庁してきた人材まで、多様なバックグラウンドや考え方を持つ職員がいる中で、チームが同じ方向を向いて進んでいけるよう、相互理解を深め、価値観を共有していけるような環境づくりに取り組んでいます。
上田 「利用者視点」の考え方ができているかどうかは、「行政機関出身者だから」、「民間出身者だから」といったバックグラウンドにはあまり関係がないと思っています。違うのは、「利用者視点」の捉え方だけ。その違いを探ってバランスを取っていくことが重要なんです。
各府省庁との立場や視点の違いを理解し、ずれを調整することが大切
―プロジェクトの中で感じている成果や変化について教えてください
大塚 クイックサーベイの存在は大きいですね。マイナポータルには、1日に数千件もの生の声が寄せられます。行政サービスに対してこれだけの反響が集まって、そのまま関係各所に共有できるのは画期的でした。集まった国民の声をエビデンスにして、迅速に改善ができる開発体制を築くことで、高い満足度が獲得できました。
上田 デジタル化によって、行政サービスが担う役割が大きく変わったと感じています。従来、政策の実行部分は、市区町村にお任せするしかありませんでしたが、デジタル化することによって、利用者の接点も含めて、私たちが作っていく必要が出てきました。だからこそ、より細かなところまで「利用者視点」が求められるようになったと思います。
行政官の仕事こそ、利用者視点であることを再認識してほしい
―より良いサービスづくりを目指す行政官にアドバイスをお願いします
大塚 繰り返しになりますが、やはり、重要なのはコミュニケーションですね。やりたいことがあるのであれば、エビデンスや背景を分かりやすくまとめた資料を作って短時間で説明する。これに尽きます。
上田 そもそも、我々行政官の仕事は国民の声を聴くことです。その本質をしっかりつかんでコミュニケーションを深めていけば、きっとより良いサービスの実現につながるはずです。