【インタビュー】 利用者視点は、新たな価値を生み出す力になる
目次
- 担当者
- これからの利用者視点と、デジタル庁が担う役割
- 利用者視点がもたらした変化。変化を広げるために必要なこと
- デジタル庁として、チャレンジしていくべき課題とは
- 利用者視点のサービスづくりに取り組む行政官に伝えたいこと
- 関連ページ
担当者
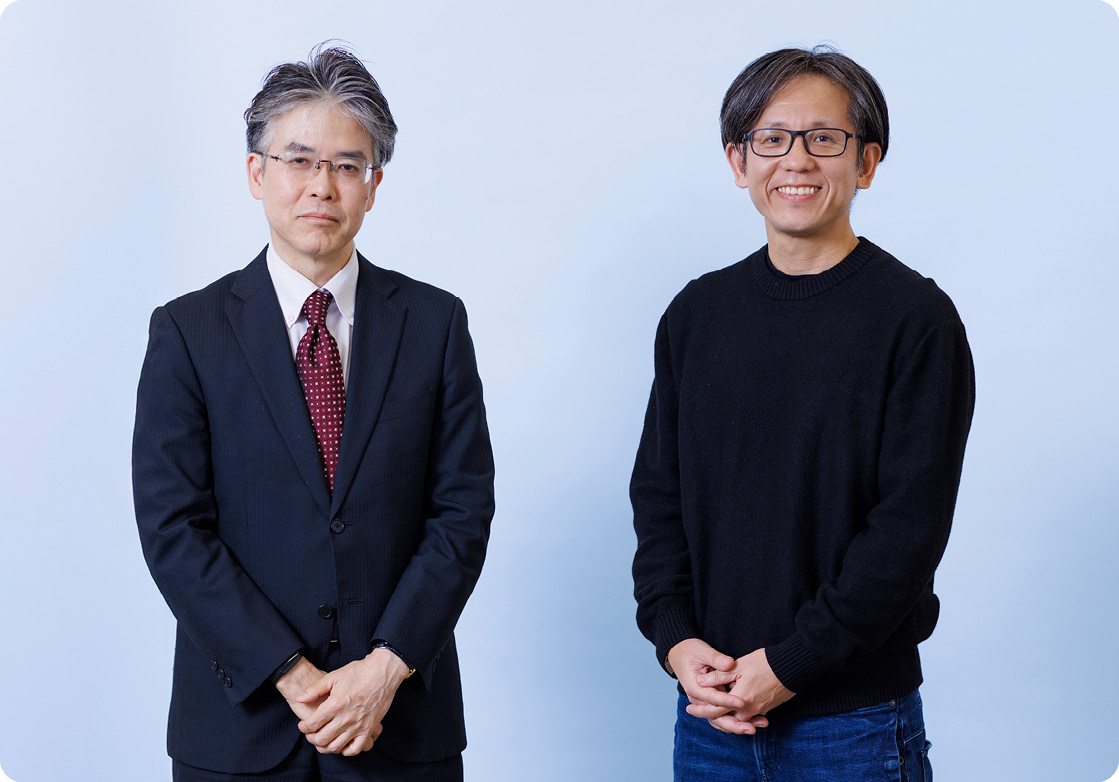
デジタル庁 デジタル監 浅沼 尚 (写真右)
民間企業勤務から、2021年デジタル庁CDO(Chief Design Officer)を経て、2022年より現職。
デジタル庁 デジタル審議官 二宮 清治 (写真左)
1988年旧郵政省入省。総務省総合通信基盤局長、デジタル庁省庁業務サービスグループ統括官等を経て、2023年より現職。
※所属・職名などは2025年4月1日現在のものです。
これからの利用者視点と、デジタル庁が担う役割
浅沼 「利用者視点」の必要性を理解する上で大事になるのは、社会の中で起こっている3つの変化を認識することだと思っています。1つめは、人々が重視する価値が「モノ」から「コト」へと変化していること。より精神的な価値を求める傾向が高まるとともに一人ひとりのニーズも多様化しています。2つめは、日本国内では人口減少とリソース不足の中で、事業活動が「競争」から「共創」に変化していること。あらゆる関係者とつながり、共に新しい価値を作り出すことが必要となります。3つめは、世の中が、「消費」から「循環」へと変化していること。エネルギーや自然資源など、限りあるリソースを、社会ニーズとバランスを取って効率的に活用することを考えなければなりません。
こうした変化において、一人ひとりの価値観や求めていることを深く理解し、関係者と共に新しい価値を作り、効率的に社会実装するための有効な手段として「利用者視点」の考え方や取組がますます重要性を増しています。
二宮 デジタル庁発足以前に時計の針を戻してみたいと思います。当時、菅元総理大臣は、「行政の縦割りを打破し、大胆に規制改革を断行する。そのための突破口としてデジタル庁を創設する」という旨をお話しされました。デジタル庁は、その改革を実行するため社会全体のデジタル化をリードする強力な組織です。「利用者視点」は、従来から重要とされてはいたものの、行政の常として、自らの責任範囲を確定し、そこに全力投球する姿勢となりがちでした。その結果、個々の担当部局の責任は果たせたとしても、全体を通じて達成したい利用者のニーズに応えられない「部分最適」に留まっていたわけです。
今求められているのは、視点を利用者側に置き換え、組織横断的に改革を進め、真の利用者ニーズに正面から応えることだと思います。また、行政側が保有する様々なデータが縦割りで、横につながっていなかったことも大きな課題でした。コロナ禍の「デジタル敗戦」を繰り返さない。この課題の解決もデジタル庁の役割だと考えています。
利用者視点がもたらした変化。変化を広げるために必要なこと
浅沼 デジタル庁が発足してから、多くの変化や成果が生まれていると感じています。まず、「利用者視点でサービスを作るための共通基盤」が整ってきたこと。デジタル庁では、デザインシステムやサービスデザインのガイドラインなどの共通ツールや、府省庁やデジタル庁のプロジェクトにおけるデザイン活動を支援するためのデザイン組織を拡充してきました。新型コロナワクチン接種証明書アプリや、マイナポータルの刷新をはじめ、多くの方々が便利になったと思えるような分かりやすい成果が出始めていることも大きいですね。次に、「利用者視点でサービスを作るための考え方や文化」が当たり前のものになりつつあること。様々なプロジェクトでサービスの利用率や満足度の分析が業務に組み込まれています。次の段階として、「利用者視点で既存の法律や制度を刷新する」、「利用者視点で政策づくりを行う」といった行政の根本的な課題解決や社会全体の仕組みづくりにも踏み込めるようになったと感じています。
二宮 こうした良い変化を広げるためにも、各組織の幹部がリーダーシップをもって、自ら行動していくことが重要です。概念的な政策目的を各々の現場レベルでしっかり噛み砕いて、自分たちの取組は全体の政策目的にどうつながるのか、また、その具体的効果は何かを考え、進捗を評価していくことが必要不可欠です。「利用者視点」の取組は、1年や2年でできることではありません。持続的に少しずつ積み重ねて、その経過をしっかり評価して改善を重ねていく。そのサイクルが大事だと思います。
デジタル庁として、チャレンジしていくべき課題とは
浅沼 デジタル庁としてチャレンジすべき課題は、「行政のデジタル改革」に留まらず、「社会のデジタル改革」を進めることです。民間企業並みのスピード感をもって社会に価値を届けること、利用者がうれしいと思えるサービスを提供し続けることが期待されていると思っています。そのためには、人や予算や時間などリソースが限られた中で、デジタル技術やデジタルツールを最大限活用し、あらゆる課題に対して「利用者視点」で取り組むことが鍵になります。
デジタル技術は変革の量を増やし、「利用者視点」は変革の質を高めると思っています。特に直近では生成AIの社会実装が進む中でこのテクノロジーを最大限活用して「社会のデジタル改革」を更にスピードを上げて推進したいと思います。
二宮 「利用者視点」のサービスづくりという視点で見れば、以前より着実に良くはなってきていると感じていますが、リソースに限りがあることは、浅沼さんがおっしゃるとおりだと思います。「デジタル行財政改革」という、政府が取り組む重点改革にも、あらゆる分野の取組に対して、常に利用者を一番に考える、ということが明記されており、政府が「利用者視点」のサービスづくりに大きく舵を切っている中で、デジタル庁としても、各府省庁、自治体と一層緊密な連携を図っていかねばならないと考えています。
利用者視点のサービスづくりに取り組む行政官に伝えたいこと
浅沼 「利用者視点」とは、「自分とは異なる他者の立場に立って物事を捉えて、他者の考えや気持ちの変化に想像力を働かせながら実践する姿勢や態度、そして他者と共感するためのアプローチやプロセス」でもあります。冒頭の話ともつながりますが、「利用者視点」を持つということは、これからの社会で求められる考え方や能力にもなると思います。また、行政の仕事に欠かせない交渉力や合意形成力を高めるための手段にもなります。
私たちが関わるプロジェクトに1人の力で完結できるものはありません。国民だけでなく、サービスを提供する府省庁や自治体の職員の方々、民間事業者や国内外の関係者の立場に立って一緒に価値を作っていく、「利用者視点」の姿勢、態度、アプローチ、プロセスが求められています。
二宮 「利用者視点」を行政の中で捉え、効果的に浸透させるためには、行政運営の基本理念として組織全体に定着させる必要があります。いわば、意識改革が重要です。
また、デジタルサービスを作ることも大切ですが、その手前にある業務のやり方を見直すことも必要ですし、それを支援するのがデジタル庁の役割の1つです。だからこそ、サービスを使う各府省庁、自治体の現場と連携していく上でも「利用者視点」が重要なんです。
浅沼 新たなメンバーでプロジェクトに取り組む際に、「利用者視点は全員が取り組む基本的な考え方だよね」という確認を行ったり、自分の組織やチームの中に、あらためて「利用者視点」を導入する際に、「利用者視点ってこういう考え方や取組事例だよね」といった共通認識を作る材料として、ぜひ日々の業務でこのガイドブックを使ってほしいと思います。
二宮 「利用者視点」の取組は、自分たちだけで考えていても答えが出ないことが多いと思います。そんなとき、このガイドブックのような分かりやすい事例があると、それがヒントになるはずです。自分たちだけで考えるのではなく、周りの活動もしっかり見て、その事例を生かすという発想を持ってもらえたらいいですね。