2025年デジタル庁活動報告
- 最終更新日:
デジタル庁が創設されて4年が経過しました。関係者と連携し、行政のデジタル改革を推進し、「生活」「事業・地域」「行政」の各領域に大きな変化をもたらしました。この4年間のデジタル改革の成果は、国民生活の利便性向上、事業や地域の活性化、行政における効率化、そして社会全体のデジタル改革の基盤となっています。
本報告では、これまでの成果と今後の取組についてまとめています。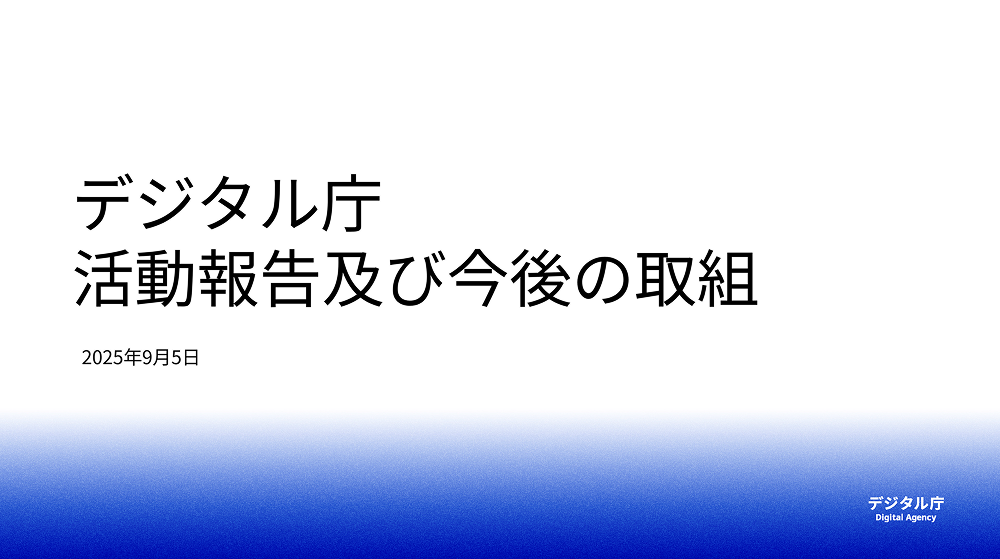
活動報告及び今後の取組
デジタル庁のこれまでの成果と今後の取組についてまとめています。詳細は以下の資料をご覧ください。
会見動画
目次
1. はじめに
活動報告とは
国民や関係者の皆様に社会のデジタル化の現在地とデジタル庁の成果を共有
2021年9月1日、日本のデジタル社会実現の司令塔としてデジタル庁が発⾜しました。
デジタル庁は、誰一⼈取り残されることなく、多様な幸せが実現できる社会を目指し、国や地⽅公共団体、⺠間事業者など関係者の方々と連携して、社会全体のデジタル化を推進する取組を牽引していきます。
本資料は、国民や関係者の皆様に、社会のデジタル化の現在地と、最新のデータに基づき、デジタル庁が取り組む施策の成果とデジタル活用の進捗を共有するものです。
デジタル活用により目指す社会
デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会
社会全体のデジタル化は、国⺠生活の利便性を向上させ、官⺠の業務を効率化し、データを最大限活用しながら、安全・安心を前提とした「⼈に優しいデジタル化」であるべきです。
デジタル技術の進展により、一⼈ひとりの状況に応じたきめ細かいサービスが低コストで提供できるようになり、多様な国⺠・ユーザーが価値ある体験をすることが可能となってきました。
デジタルの活用で目指すのは、これを更に推進し、誰一⼈取り残されることなく、多様な幸せが実現できる社会です。
デジタル社会で目指す6つの姿
- デジタル化による成長戦略
社会全体の生産性・デジタル競争力を底上げし、成長していく持続可能な社会を目指す。 - 医療・教育・防災・こども等の準公共分野のデジタル化
官民間やサービス主体間での分野を越えたデータの利活用を促進し、国民一人ひとりに最適なサービスを提供。 - デジタル化による地域の活性化
地域の魅力が向上し、持続可能性が確保された社会の実現を目指す。 - 誰一人取り残されないデジタル社会
誰もが日常的にデジタル化の恩恵を享受できるデジタル社会の実現を目指す。 - デジタル人材の育成・確保
デジタル人材が育成・確保されるデジタル社会を実現する。 - DFFTの推進をはじめとする国際戦略
国境を越えた信頼性ある自由なデータ流通ができる社会の実現を目指す。
デジタル庁の活動方針
ミッション・ビジョン・バリュー
デジタル庁では、ミッション・ビジョン・バリューを定め、これに基づいて活動しています。
詳細:ミッション・ビジョン・バリュー
2. 行政のデジタル変革と取組成果
「生活」の変化
窓口は行くからいつでもどこでもへ
- マイナポータルを利用して24時間「いつでもどこでも」手続が可能に
- 引越し、パスポート、子育て、介護などの多くの行政手続をオンラインで実施可能
- 確定申告のオンライン化と所要時間の短縮
- マイナポータル経由でデータを一括取得してe-Taxへ自動入力可能になったことにより、従来数時間かかっていた作業が短時間で完了可能に
マイナンバーカードは持つから使うへ
- 国民の約8割がマイナンバーカードを保有(2021年から2025年までの4年間)
- 「カード」または「スマホ」だけで日常の様々なシーンを便利かつ安全に過ごせる環境を整備
- 健康保険証と一体化した「マイナ保険証」の利用開始(2021年10月)
- 運転免許証と一体化した「マイナ免許証」の利用開始(2025年3月)
- スマートフォンで本人確認が完結する「デジタル認証アプリ」のリリース(2024年6月)
もしもの時も安心サポート
- 救急現場でマイナンバーカード(マイナ保険証)を活用した医療情報閲覧が可能に
- 「マイナ救急」の全国展開(2025年10月から全国の消防本部で一斉開始)
- 高額療養費制度では、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで窓口での自己負担限度額超過分の支払いが不要に
- 災害時の避難所運営の効率化(業務の約90%削減を実現)
一人ひとりに寄り添う優しいサービスに
- マイナポータルの全面リニューアル(2024年3月)
- 出生届のマイナポータルでのオンライン提出と新生児のマイナンバーカード交付申請手続の同時実施が可能に
- デジタル推進委員によるデジタルに不慣れな利用者へのデジタルサポート体制の強化
「事業・地域」の変化
制度はアナログ前提からデジタル前提へ
- 政府のアナログ規制の大幅な点検・見直しを実施(8,162条項のうち7,983条項の見直しが完了、見直し率97.8%)
- 地方自治体向けのアナログ規制見直し支援を強化
- アナログ規制の見直しが「実施済」、「実施中」及び「実施予定」の団体の割合が倍増(2024年4月末22%、2025年3月末43%)
- 「アナログ規制点検ツール」を通じた自治体や事業者の自律的な改革を支援
- 新技術を体系化したテクノロジーマップ・技術カタログの掲載件数の拡大(2025年7月時点で226件)
- ドローンによる現場点検や経年劣化・故障予測AIの実装事例が、監査や維持管理の効率化と安全性向上に貢献
手続は紙書類・郵送からデジタル・オンラインへ
- 事業者向け認証基盤「GビズID」の普及(2025年3月末時点で累計発行アカウント124万件、接続サービス数217)
- 行政手続全般を支える「e-Gov」の共通機能提供
- 補助金申請プラットフォーム「Jグランツ」の機能強化
- 政府電子調達システム(GEPS)によるオンラインでの入札・契約・請求等の支援
暮らしを支える準公共のデジタル化
- 医療面:自治体と医療機関をつなぐ情報連携基盤「Public Medical Hub(PMH)」の拡大(2025年度までに累計約600自治体が導入予定)及び標準型電子カルテα版の整備
- 防災分野:「災害派遣デジタル支援チーム(D-CERT)」の創設
- 教育分野:「教育DXロードマップ」の改定と実装
- 交通・移動分野:「モビリティ・ロードマップ2025」に基づく取組の推進(2025年度から2026年度)
データでつながる地域と事業
- 新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した地域と事業をデータで有機的につなぐ取組の具体化
- 都道府県におけるデータ連携基盤の共同利用状況の拡大
- G7広島サミットで承認されたDFFT(Data Free Flow with Trust)の具体化に向けた国際枠組みIAP(Institutional Arrangement for Partnership)の推進
「行政」の変化
行政システムは個別・単独から共通・共同へ
- GSS(Government Solution Service)の導入拡大(2025年7月時点で導入府省庁14機関、接続ユーザー4.5万人)
- 地方公共団体の基幹業務システムの標準化推進(原則2025年度末までに標準準拠システムへの移行完了を目指す)
- ガバメントクラウドの整備・運用(2025年7月末時点で4,892システムが利用)
AI活用・内部開発の加速
- 「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」の策定(2025年5月)
- デジタル庁内製開発による生成AI利用環境の活用拡大(利用者950名、利用回数延べ65,000回)
- 内部開発による迅速なサービス提供(マイナンバーカード対面確認アプリ、iPhoneのマイナンバーカード対応等)
国・地方・官民連携のデジタル改革へ
- AIアイデアソン・ハッカソンの開催
- 「デジタル改革共創プラットフォーム」への参加拡大(1,479の地方公共団体、約11,500人が参加)
- オープンデータの取組拡大(2025年8月時点で88%、1,564団体が利活用)
政策の進捗や効果は一目でわかるへ
- 政策データダッシュボードの拡充(16のダッシュボードを公開)
- 「Japan Dashboard」の公開(691指標を7カテゴリに整理し、都道府県別に可視化)
- デジタル庁ニュースやデジタル庁公式noteによる情報発信の強化
3. 今後の取組「社会全体のデジタル改革推進」
重点計画にもとづく社会全体のデジタル改革推進
行政のデジタル改革から社会全体のデジタル改革へ。AIフレンドリーな国家に。
デジタル庁創設からの4年間で、行政のデジタル改革は「社会の変化」を確かな成果として積み重ねてきました。しかし、国内には依然として多くの課題が山積しており、その解決の糸口を模索し続けています。また、国際情勢も大きく変貌を遂げました。こうした背景を受け、2025年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」では、これまでの行政のデジタル改革の成果を足がかりに、「社会全体のデジタル改革」へと着実にステップを踏み出す方針を明確に打ち出しました。
- 日本が直面する課題
- 人口減少と労働力不足
- デジタル競争力向上の必要性
- 自然災害や公共インフラ等の持続可能性への脅威への対応
- サイバー空間における脅威の増大
- デジタル人材不足
- デジタル化に対する不安やためらい
- 技術や世界情勢の変化
- AIの社会実装の進展
- デジタルを巡る国際情勢の変化
これらの課題や技術革新、そして世界情勢の変化を踏まえ、デジタル庁は行政のデジタル改革を土台に、日本社会全体のデジタル改革を力強く推進するとともに、関係府省庁との連携を強化し、「AIフレンドリーな国家」を実現するために取組を加速させます。
- デジタル庁における今後の重点的な取組(5つの柱)
- AI・デジタル技術等のテクノロジーの徹底活用による社会全体のデジタル化の推進
- AIフレンドリーな環境の整備(制度、データ、インフラ)
- 競争・成長のための協調
- 安全・安心なデジタル社会の形成に向けた取組
- 我が国のDX推進力の強化(デジタル人材の確保・育成と体制整備)
政府のAI活用推進
政府AI基盤「ガバメントAI」を構築
政府内におけるAIの利活用のさらなる加速と将来的な地方自治体へ展開を推進します。
- 「ガバメントAI」の構築と関係機関や民間事業者との協業推進
- AI調達・利活用ガイドラインに基づく各府省庁CAIOなどの体制整備
- 「デジタル原則適合性確認プロセス(デジタル法制審査)」の推進
利用者視点のサービス拡充
一人ひとりに最適なサポート型行政サービスへ。サービスをひとつにまとめてより便利に
個人向けや事業者向けの行政サービスをさらに洗練させ、一人ひとりのニーズに最適化されたプッシュ型のサービスとして「サポート型行政サービス」を目指します。
- 「新たなマイナポータルアプリ(マイナアプリ(仮称))」のリリース(2026年8月目標)
- 事業者向けサービスの入り口を「Gビズポータル」に統合(2026年春アルファ版リリース予定)
- 「制度、業務、システムの三位一体の改革」の推進
- ベース・レジストリ(公的基礎情報データベース)の整備・運用
競争・成長のための協調
AIを前提として国内外でデータ利活用を加速。国地方のシステム最適化も推進
政府と準公共領域において、データ連携とデータ利活用を支える制度や共通基盤の整備を加速させます。
- 「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」に基づく全体設計の確立
- DFFTの実現に向けた国際的な取組の推進
- 国の情報システムの最適化(共通化、共同化、標準化の徹底)
- 地方公共団体の標準準拠システムへの移行支援
4. 組織の強化「デジタル庁2.0へ」
次世代の組織づくりを継続進化
デジタルファーストを発展させAI・データを最大限に活用する行政組織へ。世界をリードする官民一体の組織づくりを。
上記の方針を実現し、社会全体のデジタル改革を強力に推進します。
- 「AI・データファースト」の行政組織「デジタル庁2.0」を目指す
- 民間出身者と行政職員の混成による約1,500人規模の組織体制構築
AI・データ前提組織
AI・データを活用した政策立案・サービス提供・組織変革をあたりまえに
AI・データ活用を前提とする組織運営を目指します。
- 「ガバメントAI」の組織内での徹底活用
- 政策立案に関連するデータの見える化推進
- 組織内でのデータに基づくプロジェクト推進の取組
政策立案+内部開発の機能強化
利用者体験向上、政策立案から実装までの時間短縮
政策立案と内部開発を両輪とする組織強化を行います。
- 政策立案機能の強化(官房機能と企画機能の明確な分離)
- 内部開発体制の強化(特にAI実装の体制強化)
関係者との価値づくり
国民、事業者、府省庁、地方自治体との連携や支援の強化
関係者との連携や協業を積極的に主導する組織へ。
- ユーザーからのフィードバックをサービスに反映する仕組みの整備
- 各府省庁との連携強化(PMO支援、DXSの活用)
- 地方自治体との連携強化(コスト最適化支援、デジタル改革共創プラットフォームの活用)
最後に
デジタル庁は「誰一人取り残されない人に優しいデジタル化」を目指し、関係者とともにテクノロジーの力で日本全体を前進させ、社会全体のデジタル改革を進めていきます。